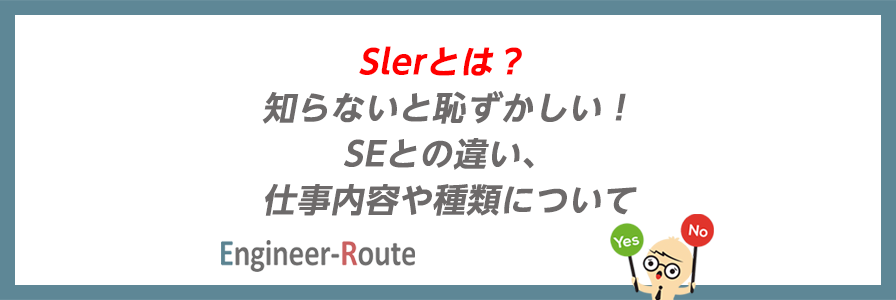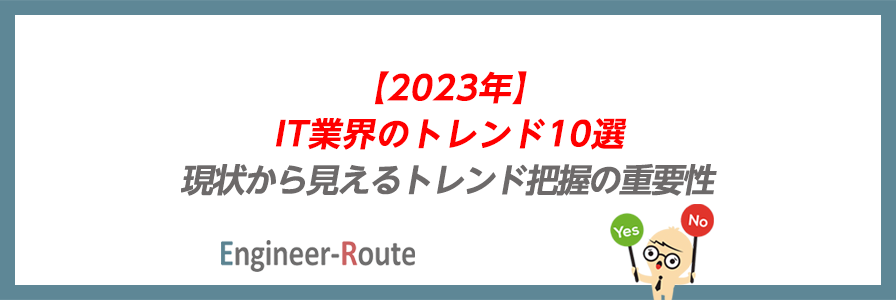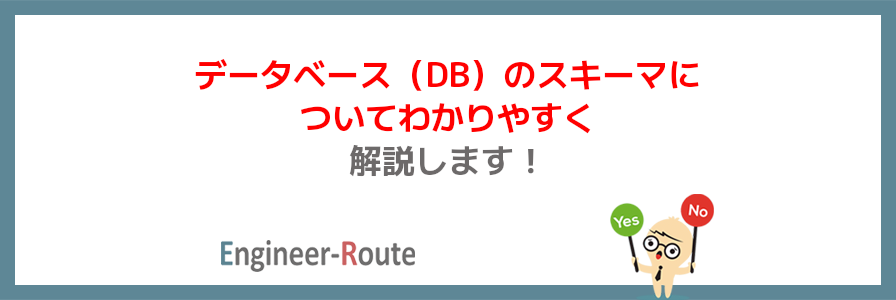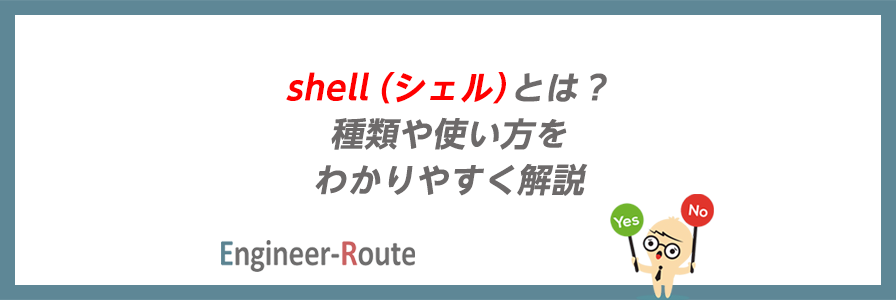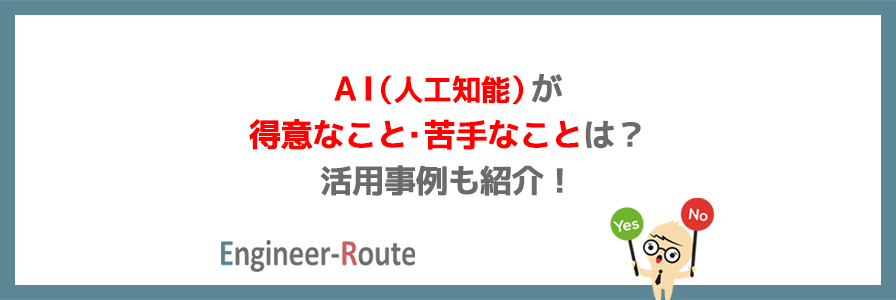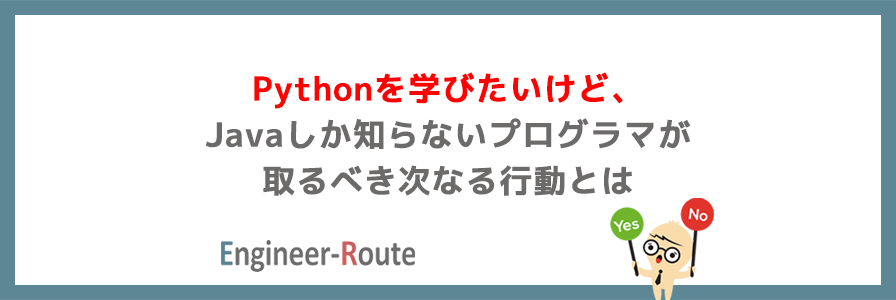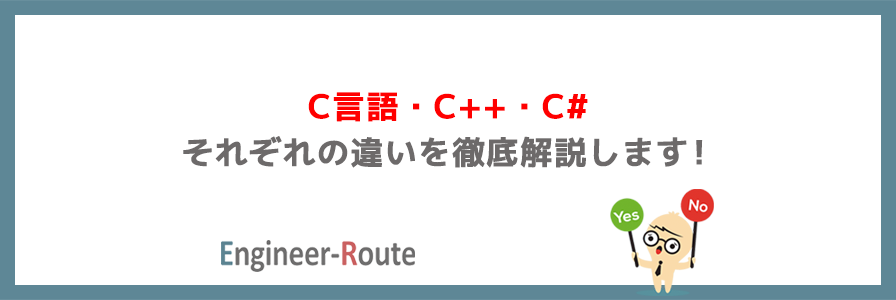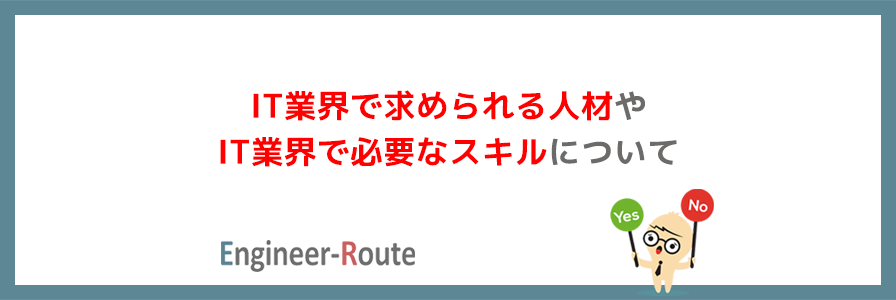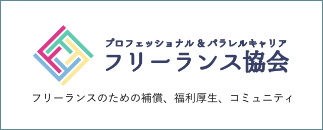セキュリティエンジニアが「やめとけ」と言われる理由5つ
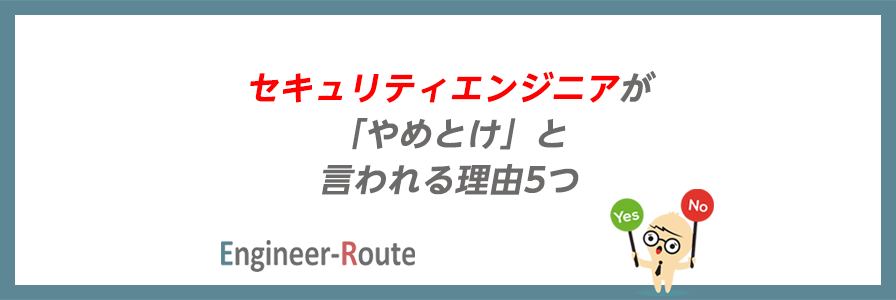
現在エンジニアとして働いており今後セキュリティ分野のエンジニアを目指しているという方、未経験だけれどセキュリティエンジニアに興味があるという方の中には、「セキュリティエンジニアはやめとけ」と言われたり、耳にしたりした方もいるのではないでしょうか。
不安や疑問をお持ちの方に向けて、今回はなぜセキュリティエンジニアが「やめとけ」と言われてしまうのか、その理由をセキュリティエンジニアのキャリアパスなど将来性とともにご紹介したいと思います。
目次
そもそもセキュリティエンジニアとは?

そもそもセキュリティエンジニアとは、その名の通り情報セキュリティを専門に扱うエンジニアです。
システムそのものや顧客の個人情報などをハッキングやコンピューターなどのサイバー攻撃、さらには情報漏洩から守るのがセキュリティエンジニアの役割です。
未然にサイバー攻撃を防ぐための調査から、ネットワークなどのインフラやそれぞれのシステムのセキュリティ対策を行うためのセキュリティシステムの提案から設計、脆弱性のテスト、実際にそれを実装し、運用から保守業務に至るまで、セキュリティに関する一連の業務を担います。
企業のDX化など、ITの進歩につれて業務における重要なシステムや情報は増え、それとともにウイルスなどシステムの安全を脅かす脅威が年々悪質化しているために、セキュリティの強化は非常に重要になっていますね。
もちろん企業だけでなく、時には交通インフラのような大規模なものから家電などの身近なものまで、あらゆるシステムのセキュリティ上の課題解決を行う役割をしているのが、セキュリティエンジニアという職種なのです。
セキュリティエンジニアはやめとけと言われる5つの理由
そんな重要な役割を持つセキュリティエンジニアですが、経験者や周りから「やめとけ」と言われがちであることも事実です。
ではなぜ、セキュリティエンジニアは「やめとけ」と言われてしまうのでしょうか。
その理由を5つ、ご紹介します。
(1)重い責任を背負わなければならないため
まず、セキュリティを担うセキュリティエンジニアは他のエンジニアと比較して責任が重いというところがあります。
サイバー攻撃やウイルス感染での情報漏洩などがもしも起こってしまうと、企業の活動自体が停止してしまったり企業の信頼を損なうことになったりと多大な被害になってしまうことがあります。
企業活動にとって非常に重要な役割を持つセキュリティを担当するには、重い責任を背負い神経を尖らせて業務に当たらなければならないということになり、そのプレッシャーから精神的に負担がかかりやすい職種だと言えるでしょう。
(2)常に迅速な対応が求められるため
セキュリティ上で何かトラブルがあった場合には、情報漏洩など最悪の事態を防ぐために迅速に対応する必要があります。
トラブルは曜日や時間を問わず突然起こるものです。
時には休日や夜間にもトラブル対応に当たらなければならないこともあるというのが、精神的にも体力的にもきついと言われる大きな理由でしょう。
(3)クライアント対応が大変なため

クライアントのシステムセキュリティを管理する上で不具合があった場合やトラブルが発生した場合には、それを解消するためにシステムの稼働を停止しなければならないことも多くあります。
システムを停止することはクライアント先企業にとって機会や金銭的な損失になりうることもありますので、クライアント先に説明し、納得してもらわなければなりません。
クライアントの担当者にはセキュリティ知識がないことも多く、そういった説明対応などが大変だというのも、理由のひとつです。
(4)トラブル発生時の原因調査が大変なため
セキュリティ上にトラブルが発生した際には、もちろん対処のために原因を突き止めるのもセキュリティエンジニアの業務です。
しかし、この原因調査の範囲が非常に広く、大変なのです。
時間がかかっても原因がはっきりと分からない場合もあり、やっと原因が分かって改めて対策をとるにも内容によってはまた1からシステムを構築しなければならないなど、原因調査から対策まで非常に負担が大きいことも、「やめとけ」と言われる理由になりますね。
(5)激務のわりに感謝をされることが少ないため
これまで説明したようにプレッシャーや責任も多いセキュリティエンジニアの仕事は、激務であるわりに感謝されるということは少ないと言われます。
IT化が進む現代ではセキュリティ対策は「出来ていて当たり前」といったような認識をされがちです。
迅速にトラブル対応を行っても慎重にセキュリティシステムを構築しても感謝されるということは少なく、モチベーションが保ちにくくなってしまいます。
セキュリティエンジニアの将来性
様々な理由からセキュリティエンジニアは「やめとけ」と言われがちな職種です。
しかし、将来性は高く、今後も変わらず需要があるエンジニアであるという一面もあります。
企業のDX化が進み、AIなどが発達してIoTも広がりを見せているようにIT業界は進化し続けており、利便性が向上するのとともにセキュリティのリスクも非常に大きくなっています。
サイバー攻撃もテクノロジーの進化とともに常に巧妙化しており、対策には専門的なセキュリティ知識をもつエンジニアが必要とされます。
そのためサイバー攻撃からシステムを守る重要な人材としてセキュリティエンジニアの需要は今後も増加していくことが考えられ、将来性は高いと言えますね。
責任は重くプレッシャーのかかる業務ではありますがその反面、システムや情報を守る無くてはならない職種として、やりがいも感じられるでしょう。
セキュリティエンジニアのキャリアパス
セキュリティエンジニアには現場でセキュリティエンジニアとして活躍し続ける方もいますが、中にはセキュリティエンジニアからさらにキャリアアップする方もいます。
セキュリティエンジニアのキャリアパスとして代表的なものを3つ、ご紹介します。
セキュリティアナリスト
より高度な知識やスキルを活かして、サイバー攻撃の際に攻撃手法の分析をすることを主な業務としているのがセキュリティアナリストです。
攻撃元が分かりにくいサイバー攻撃の攻撃手法をいち早く分析・断定しそれに応じた対策をとることが重要になるため、セキュリティエンジニアとしての豊富な経験やより専門的な知識が必要となる職種です。
セキュリティコンサルタント
セキュリティの専門知識を活かして、企業のセキュリティに対してアドバイスやサポートなどのコンサルティング業務を行うのがセキュリティコンサルタントです。
クライアントと直接コミュニケーションをとり、課題を把握するためのコミュニケーションスキルや、セキュリティの知見のみならず経営的な視点も必要になります。
ホワイトハッカー
ホワイトハッカーとは、サイバー攻撃を行う「ブラックハッカー」と呼ばれるハッカーに対抗して、攻撃からシステムを守るのが仕事です。
コンピュータやネットワークのセキュリティに関する高い技術を持ち、合法的かつ倫理的な方法でシステムの脆弱性を見つけ、改善することを目的としています。「善良なハッカー」とも呼ばれ、企業や政府機関などから依頼を受け、サイバー攻撃に備えるために防御力を強化する役割を担っています。
ホワイトハッカーは、一般的にペネトレーションテスト(侵入テスト)を実施し、システムが攻撃に対してどれだけ耐性があるかを評価します。これにより、システムの脆弱性やセキュリティホールを特定し、悪意のある攻撃(ブラックハッカー)から守るための対策を講じます。彼らの活動はセキュリティ向上に貢献し、個人情報や機密データの保護に重要な役割を果たしています。
まとめ
今回はセキュリティエンジニアに興味があるという方に向けて、セキュリティエンジニアの概要や「やめとけ」と言われる理由、また将来性など詳しくご紹介しました。
確かに激務であるなど大変なことは多いエンジニア職種ですが、その分やりがいもあり、将来性も高いのがセキュリティエンジニアです。
キャリアアップを目指すこともできる魅力のある職種ですので、ぜひ目指してみてはいかがでしょうか。