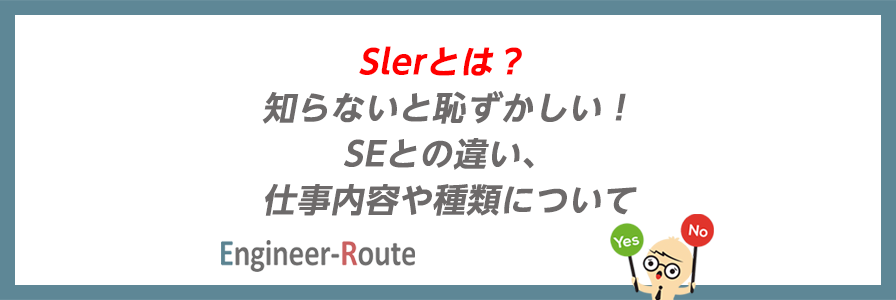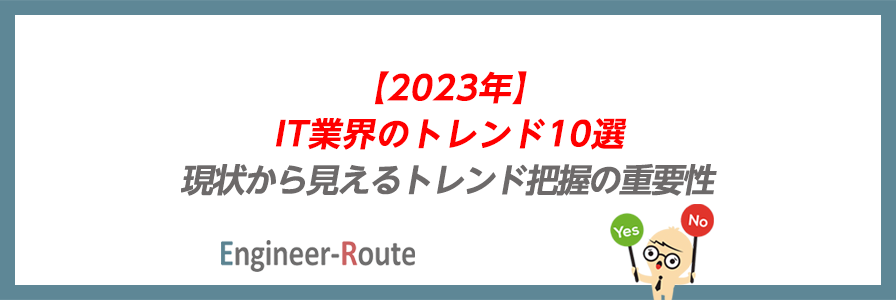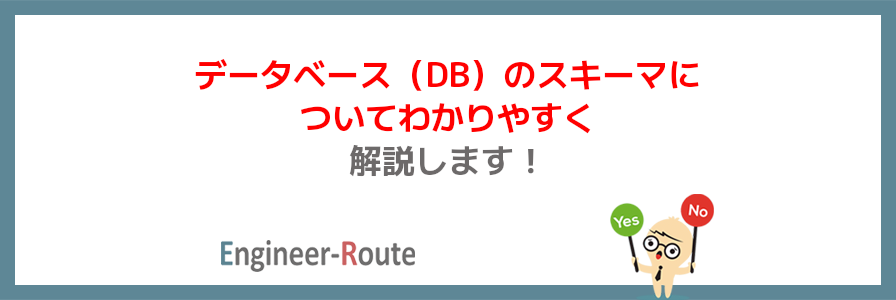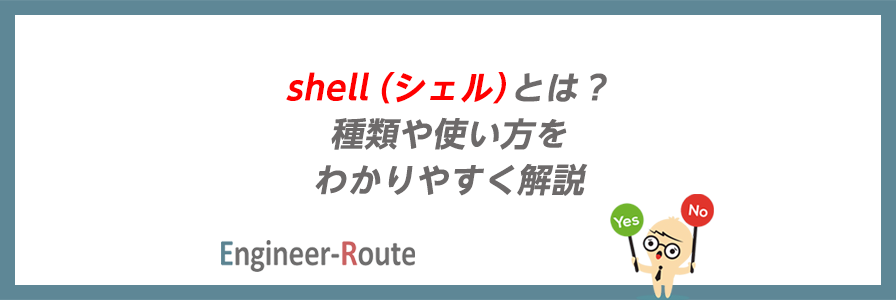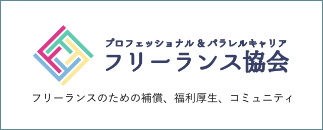フリーランスエンジニアが経費にできる項目11つ|経費率・注意点も
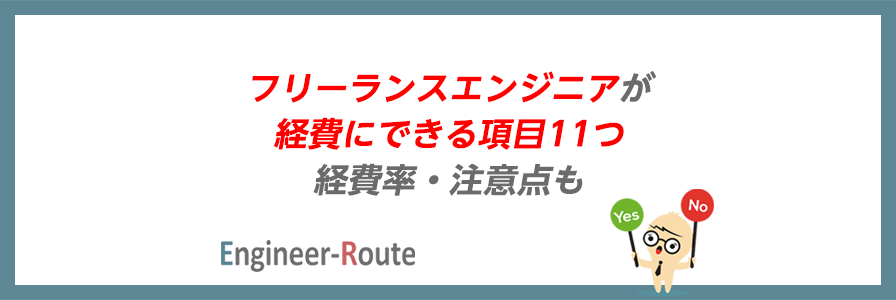
フリーランスのエンジニアとして活動し始めて、悩むのが確定申告ですよね。
そこで大事になるのが、経費の問題です。
「これは経費にできるのか?」など、疑問がある方も多くいらっしゃると思います。
今回はそんな人に向けて、フリーランスエンジニアが経費にできるものについてご紹介します。
目次
【フリーランスエンジニア】経費率の目安

経費を計上する上で、知っておかなければならないのが経費率です。
もちろん、経費が多ければ多いほど所得税額が節約できることになりますが、だからといって収入に対してあまりにも経費が多ければ税務調査で怪しまれてしまうこともあります。
そこで、収入に対する経費の割合、経費率がどのくらいになっているかを目安として考えなければなりません。
この経費率は、次の式で算出できます。
| 経費率 = 経費 ÷ 収入 |
経費率の目安は業種によっても異なり、フリーランスのエンジニアの場合では一般的に50%が目安になると言われています。
この数字は売上の規模などによっても変わってきますが、大体50%と考えておくと良いですね。
正しく経費を計上し、この目安をあまりにも上回ることのないよう注意しましょう。
フリーランスエンジニアが経費にできる主な項目11つ
ではここからは、実際にフリーランスエンジニアが経費として計上できる項目について見ていきましょう。
(1)地代家賃・水道光熱費
自身で事務所として借りている場所がある場合は、その家賃や駐車場代などを経費として落とすことができます。
そこでかかった水道光熱費なども同様ですね。
レンタルオフィスなどを借りてそこで仕事をしている場合のレンタルオフィスの月額費用も、同様に経費にできますね。
あくまで事務所利用分のみで、常駐フリーランスエンジニアの場合や自身で契約している物件ではない場合は経費にはできません。
自宅を事務所にしている場合は、家賃に関しても水道光熱費に関しても、面積と使用時間などから仕事に使用した分だけを算出して一部を計上することができます。
(2)消耗品費
使用期間が1年未満、または価格が10万円以下のものは消耗品として計上できます。
文房具や名刺、帳票といったものから、10万円以下であればデスクや椅子、パソコンといったものまでこの項目で計上可能です。
日常的に必要なものはこちらになるので、クリーニング代などの雑費と混同しないように注意しましょう。
(3)事務用品費
消耗品と同様に使用期間1年未満、価格10万円以下の文房具に関しては事務用品費として計上することもできます。
消耗品として計上しても問題ありませんが、使用頻度や購入頻度の高い文房具は消耗品と分けてこちらで計上した方が管理の面では良いですね。
毎回異なる項目で計上するのは避けて、どちらかと決めたら統一するようにしましょう。
(4)通信費
インターネット代や電話代、また宅配便の配送料、郵送費も通信費として計上できます。
インターネットを利用するためのプロバイダ料金や設置工事にかかった費用も同様に通信費として問題ありません。
ただ、電話やインターネットなど、プライベートでも使用するという場合は家賃同様割合を算出する必要があります。
(5)外注費
受注した業務の一部を他の協力会社やフリーランスに外注した場合、その報酬は外注費として経費にできます。
フリーランスエンジニアでは、専門でないデザインなどを他者に依頼することも多くあるでしょう。
注意しなければならないのは、依頼する業務によっては源泉徴収を行わなければならない点です。
例えば、上にも挙げたデザインや原稿の執筆といった業務の場合ですね。
外注の際には、事前に源泉徴収の対象になるか調べておくと良いでしょう。
(6)新聞図書費
事業に必要な新聞や書籍、雑誌などは新聞図書費として計上可能です。
例えば、フリーランスエンジニアであればスキルアップに必要なITの専門書や技術書などですね。
手元に残る書籍だけでなく、電子書籍やメルマガ、情報サイトの料金なども対象となります。
(7)旅費交通費

業務のための移動にかかった交通費や宿泊費は、旅費交通費として形状することになります。
電車やバス、タクシーといった公共の乗り物から、自家用車のガソリン代などですね。
どこからどこまでを何を利用して移動したのか、しっかりと記録しておくことをおすすめします。
領収書の出ない電車などの場合は、自身で出金伝票を作成しておくようにしましょう。
(8)接待交際費
クライアントとの打ち合わせでかかった飲食代や、仕事の付き合いで発生した飲み会などの費用は、接待交際費として経費計上することが可能です。
税務署にとってもプライベートと仕事の見極めが難しい項目で、不正が行われやすいため調査の際に注視される項目でもあります。
日付と時間などを領収書やレシートとともにしっかり記録しておきましょう。
(9)広告宣伝費
自身の広告・宣伝となるようなものは広告宣伝費として経費の対象となります。
例えば、フリーランスエンジニアでは以下のようなものですね。
| 名刺 |
| 年賀状 |
| ポートフォリオの作成費 |
広告宣伝費は上限となる金額がないため、自身や自身のスキルの宣伝効果が期待できるものは全額計上することができます。
(10)租税公課
所得税や法人税と住民税以外の税金は、租税公課として経費の対象になります。
オフィスの固定資産税や仕事で使用する車の自動車税、また契約書などの公的書類の発行にかかった手数料などが租税公課にあたります。
所有者が事業車本人でなければ認められない場合が多いので注意しましょう。
(11)諸会費
勉強会やセミナーの会費、オンラインサロンやフリーランス協会の会費、また有料のオンラインツールを利用するための登録費など、仕事に関係する会費は諸会費として計上できます。
フリーランスエンジニアでは、特にオンラインツールの利用なども多いのではないでしょうか。
支払いを証明する書類のコピーはしっかりと保管しておきましょう。
フリーランスエンジニアが経費計上するときの注意点
フリーランスエンジニアが経費計上する際に注意点しなければならないのは、主に
- 過度に経費を計上しすぎないこと
- 必ずレシートを保管しなければならないこと
の2点です。
はじめにご紹介した経費率の目安を大きく超えてしまうと、税務調査の対象になってしまいます。
調査が入れば仕事のスケジュールにも影響が出てしまいますし、取引先に迷惑がかかることにもなりかねません。
経費計上できないものはしっかりと把握して、申告の際に経費率の目安を超えたら再度経費の見直しを行うなどして、過度に計上しないように注意しましょう。
また、経費計上の際の証明のために必ずレシートは保管しておきましょう。
フリーランスエンジニアでは、レシートを領収書として扱うことができます。
まとめ
今回の記事では、確定申告の際の経費計上に悩むフリーランスエンジニアに向けて、経費として計上できる項目と注意点について詳しくご紹介しました。
経費率やレシートの保管など、注意しなければならない点は多くありますが、経費をしっかりと計上することで節税につながります。
確定申告の際はぜひこちらの記事を参考にしてみてくださいね。