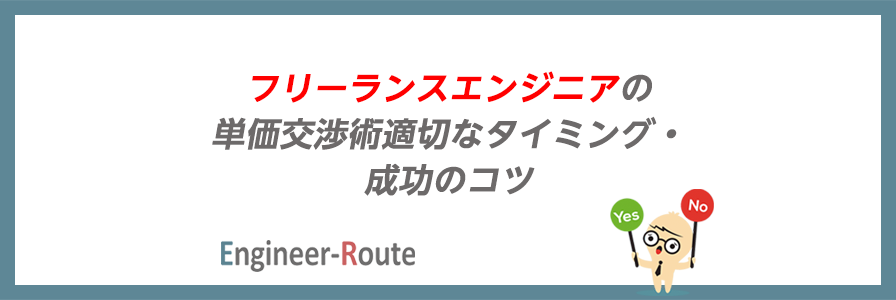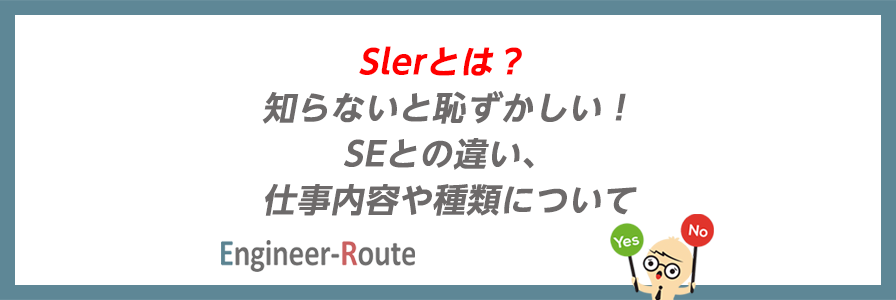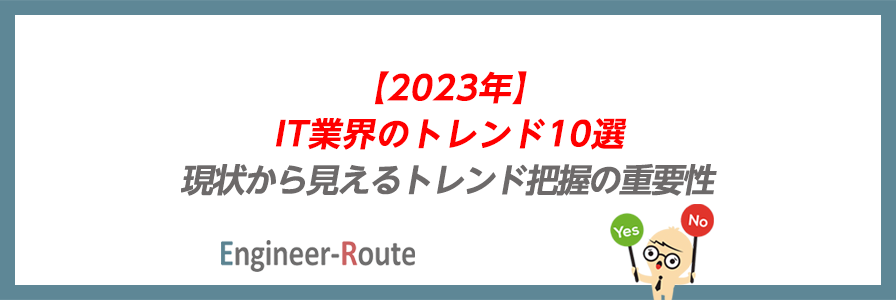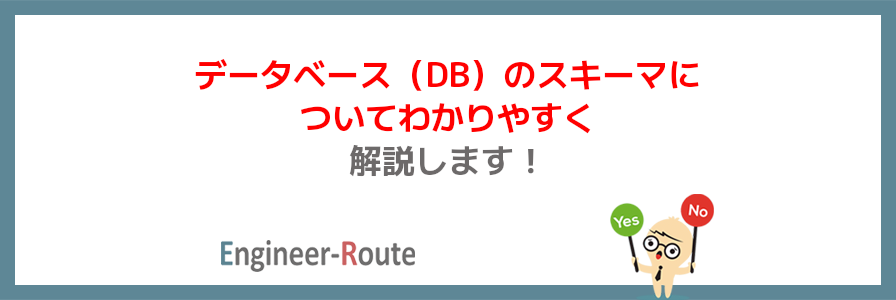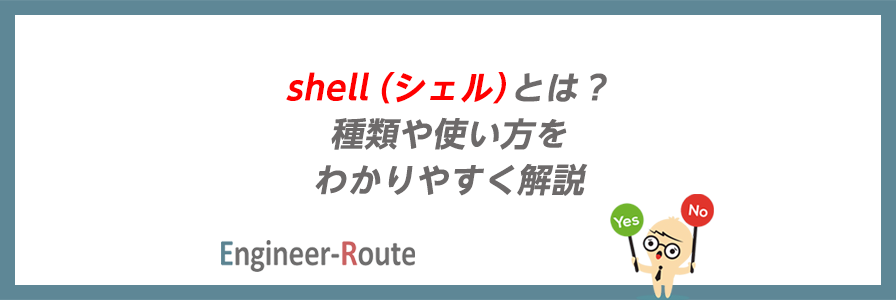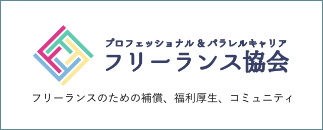フリーランスエンジニアの単価の決め方|注意点・単価アップの方法も
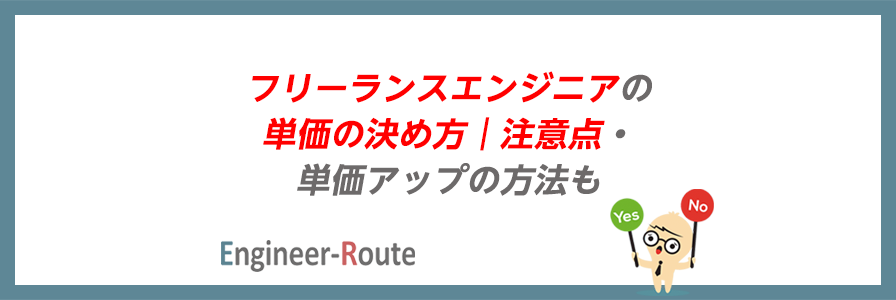
フリーランスエンジニアとして働き始めたばかりだという方の中には、
「案件を獲得できそう!だけど単価はどのように決めればよいのだろう……」
「単価の相場はどれくらい?」
といった疑問や悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそういった方に向けて、フリーランスエンジニアの単価の決め方や相場、注意点などを詳しくご紹介したいと思います。
目次
1. フリーランスエンジニアの単価の決め方

フリーランスエンジニアが単価を決める際には、基本的に以下の3つのポイントを考慮して決めることになります。
1-1. 相場
まず、単価を決める上で一番の基準となる最も重要なポイントと言ってよいものが、相場です。
その案件の業務内容や職種などによって単価の相場には違いがあります。
相場を確認することで、クライアントにとっても自分にとっても高すぎず安すぎず適切な単価というものがどの程度なのかが分かり、ひとつの大きな基準にすることができます。
案件が決まったときにはフリーランス案件情報サイトやクラウドソーシングサイトなどで同様の案件を調べて、単価相場を確認するようにしましょう。
1-2. 自身の保有スキル・経験
もうひとつ、単価を決める上で加味しなければならないのが、自身の保有するスキルと実績・経験です。
スキルに自信が無かったり、実務経験が浅くクライアントが期待するレベルに満たない場合は、相場よりも低い価格での依頼を提示されることがあります。
逆に、実績が豊富であったり、高いスキルを持っていてクライアントが求める以上の業務を行えれば相場よりも高い単価でも受注できることもあります。
相場と自分の持つスキルや経験を照らし合わせ、金額が見合っているかを考えて単価を決めるようにしましょう。
業務に要する時間がどれくらいかなどを想定し、時給に換算してみるのも分かりやすいかもしれません。
1-3. 取引先企業の予算
フリーランスエンジニアに報酬を出すのは、案件を依頼したクライアント企業です。
取引先となる企業側の予算や状況も十分考慮して単価を決定するようにしましょう。
時には企業側の目線に立って、どれくらいの金額であれば自分のようなエンジニアに依頼するかを考えるのも大切です。
低く設定しすぎることでスキルに自信が無いと思われてしまう場合などもありますね。
自分の生活やスキルレベルと企業側の状況、両方のバランスがとれる金額設定を心がけましょう。
2. フリーランスエンジニアの単価相場|職種別・言語別に紹介!
フリーランスエンジニアが案件を受託する際、報酬は基本的に月単価で提示されるのが一般的です。
一口にエンジニアといっても、職種や使われる言語など案件ごとに単価相場が異なります。
ここでは職種別・言語別に月単価の相場をそれぞれご紹介します。
2-1.【職種別】フリーランスエンジニアの月単価相場
まずは、職種ごとの月単価相場です。
| 職種 | 月単価 |
| PM(プロジェクトマネージャー) | 約80万円 |
| SE(システムエンジニア) | 約70万円 |
| インフラエンジニア | 約70万円 |
| プログラマー | 約60万円 |
| テスト/検証エンジニア | 約55万円 |
プロジェクトをマネジメントする役割であるプロジェクトマネージャーなど、いわゆる上流工程を担当するエンジニアはより高いスキルや経験を要求されるため、比較的月単価が高くなっています。
システムエンジニアやインフラエンジニアなども平均をとるとこのような金額ですが、もちろん上流工程を担当するか下流の工程を担当するかで、自身のスキルや経験によっても単価は変わってきますね。
反対に、下請けに多く見られるテストエンジニアやプログラマーなどは、経験が浅くても可能な案件が多いため単価相場が低くなっています。
2-2.【言語別】フリーランスエンジニアの月単価相場
次に、取り扱う言語別での月単価相場です。
| 言語 | 月単価 |
| Java | 約70万円 |
| JavaScript | 約65万円 |
| PHP | 約70万円 |
| C# | 約70万円 |
| Python | 約80万円 |
| Ruby | 約75万円 |
| Go言語 | 約80万円 |
このように、知名度が高く開発の主流となる言語は比較的単価が高い傾向にあります。
中でも新しめの言語であるGo言語や、近年開発が進み注目を浴びているAIやディープラーニングなどの分野で多く使われているRubyなどは特に高単価の案件が多くありますね。
しかし、職種と同様に単価にはスキルレベルが大きく関わります。
自らがどの程度のスキル・経験がありどの範囲まで業務をこなせるかを考慮して、上の相場はあくまで参考程度にしましょう。
3. フリーランスエンジニアが単価を決める際の注意点

相場などを参考に最終的に単価を決める際には、以下の2つの点に注意しましょう。
無理に単価を下げない
とにかく案件を受注することだけを考えて低すぎる単価を提示しないように注意しましょう。
無理に安売りしてしまうと生活にも不安が残る上、モチベーションの低下にもつながりかねません。
クライアントが「この金額で良いんだな」と一度考えてしまうと、その後そのクライアントへ単価の交渉をすることも難しくなってしまいます。
クライアントに値切られたとしても、生活とのバランスやその後の繋がるかのメリットを考えてデメリットの方が大きいようであれば、無理に安く受注するのはやめましょう。
相場をそのまま反映しない
単価の決め方に悩み相場を参考にするのは良いのですが、あくまで相場は参考程度に留めるように気をつけましょう。
たとえ職種や言語などが同じでも、個人個人の実績やスキルレベル、またクライアント側の状況などによっても適切な単価は変わってくるため、相場を絶対的な基準として考えるのはリスキーです。
インターネットなどで調べて出てきた相場をそのまま反映しないように注意しましょう。
4. フリーランスエンジニアが単価アップを叶えるためには?
単価を決めて契約し、案件をこなせるようになったフリーランスエンジニアの方は、次のステップとして単価アップを目指すことになるでしょう。
ですが、こちらが何も言わなくても企業側が善意で単価を上げてくれるということはほとんどありません。
フリーランスエンジニアが現在の受注単価をアップさせるためには、自らクライアント企業と単価交渉を行うことが必須になります。
単価交渉は、まず交渉に必要な材料を揃えるところから始まります。
実績やスキルなどの付加価値がなければ、クライアントは単価を上げることに納得してくれません。
高いスキルを身につけることやこれまでの実績を具体的にまとめるなどして交渉材料を揃えましょう。
前提として、普段からクライアントと信頼関係を築いておくことも重要になります。
日が浅かったり仕事の姿勢に不安のあるエンジニアに単価を上げてほしいと言われても、承認することはできないでしょう。
材料が集まったら、契約更新や新たな案件が始まるタイミングなど適切なタイミングを見計らって交渉材料とともに提案しましょう。
このときにもはじめの単価決定の時と同じように、スキルや実績に見合った希望単価を提示することが大切です。
交渉が成功すれば、晴れて単価アップとなりますね。
単価交渉のさらに詳しいやり方やポイントについては、下記記事を参考にしてみてください。
まとめ
今回の記事では、単価の決め方に不安があるフリーランスエンジニアの方に向けて、単価の決め方や相場、注意点などを詳しくお話ししました。
フリーランスエンジニアの単価決定は相場が基準となりますが、自身のスキルや経験、また取引先企業側の予算や状況などを大きく考慮しなければなりません。
また、後の単価アップには単価交渉が重要になります。
単価の決定や単価交渉の際には、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。