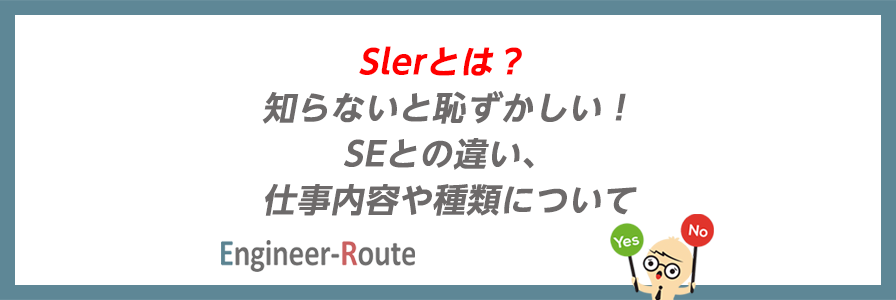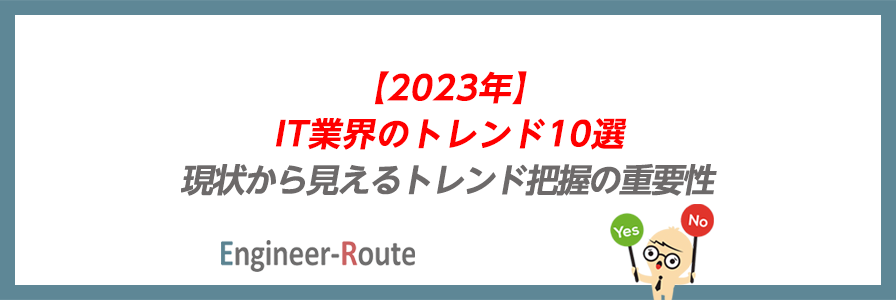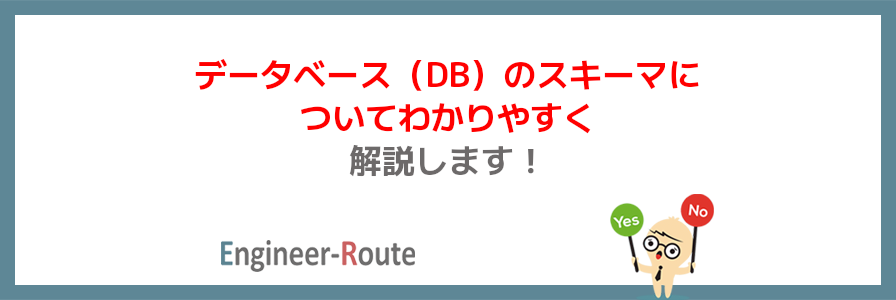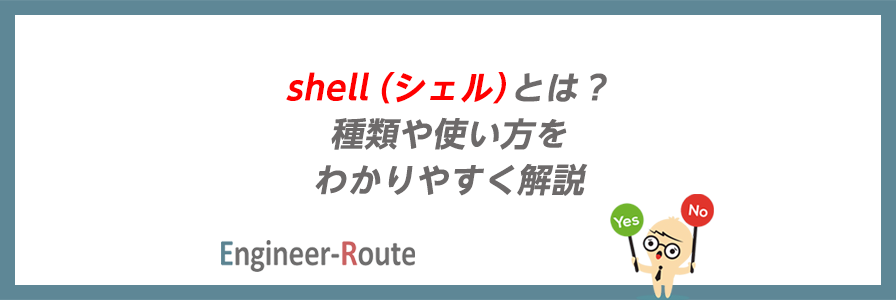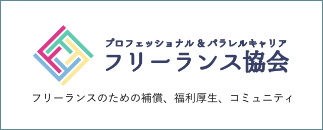フリーランスエンジニアの手取り収入と税金額|収入を上げるコツも
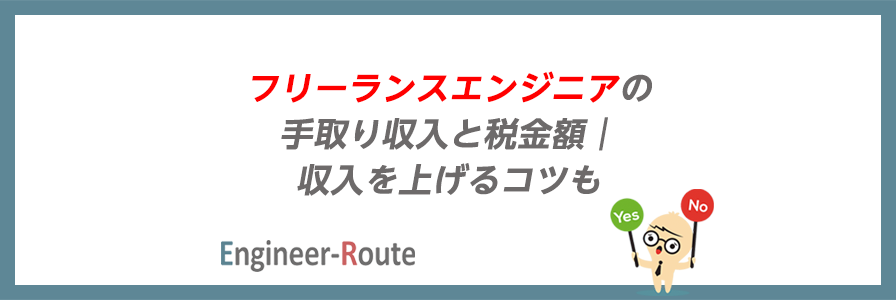
フリーランスエンジニアとして働き始めるとひとつの大きな問題となるのが、お金の問題です。
企業勤めのときには会社が行ってくれていた保険や各種税金・確定申告などの手続きなどはすべて自分で行わなければならず、案件を獲得して収入を得たからといってそのすべてが自分の手取り収入となるわけではありません。
今回はフリーランスエンジニアとして独立したてで不安や疑問をお持ちの方に向けて、実際の手取り収入や税金、さらには節税方法までをご紹介したいと思います。
目次
フリーランスエンジニアの「手取り収入」とは?
企業に勤めるエンジニアは社会保険料や税金などをすでに会社が給与から天引きしたものを受け取るため、その受け取った額が「手取り収入」となります。
しかし、フリーランスエンジニアの場合は案件を終えてクライアントから貰った報酬すべてが収入となるわけではありません。
月の報酬を「売上」とし、そこから業務の上で必要なものを購入するための経費や保険料・税金などを差し引いた額を「手取り収入」とします。
冒頭でもお話したようにこれらを支払う手続きや収入の管理なども、個人事業主として働くことになるフリーランスエンジニアでは自分でおこなわなければなりません。
フリーランスエンジニアが納めるべき税金の主な種類3つ
それではまず、売上から税金として納めなければならない税金の種類にはどんなものがあるかご紹介します。
フリーランスエンジニアが納めなければならない税金は、主に以下の3種類になります。
所得税
まずは、所得収入に対してかかる所得税です。
1年間の所得から経費や全員が適用できる基礎控除などの様々な控除分を引いた額に対して課税されるもので、日本は超過累進税率といって195万円までは5%、330万円までは10%、695万までで20%……といったように、所得が多ければ多くなるほど課税率が高くなる仕組みになっています。
詳しくは国税庁「所得税のしくみ」を参照して下さい。
消費税
サービスを受けたり何かを購入したりしたとき消費者にかかる消費税も、消費者が一時的に負担し企業や事業者に対して支払いの義務があるものです。
そのため、個人事業主となるフリーランスエンジニアが支払わなければいけない税でもあります。
現在は基準期間(納付義務が発生する2年前)課税対象となる売上が1000万円以上となった事業主のみが課税対象となっているため独立したてには発生しないものですが、計算方法や納付義務の対象が複雑であるためきちんと調べておきましょう。
税理士などに相談するのも良いかもしれません。
詳しくは国税庁「消費税のしくみ」を参照して下さい。
住民税
行政サービスの費用負担のために都道府県や市区町村など、住んでいる地域の自治体に納めるのが住民税です。
定額で負担する「均等割」と所得金額に応じて支払う「所得割」があり、地域によっても多少の差はありますが所得割の標準税率としては区民税や市町村民税が6%、都民税や道府県民税が4%となっています。
住民税に関しては地域の役所が計算したものが毎年通知されるため、それに応じて支払えば問題ありませんね。
詳しくは財務省「もっと知りたい税のこと」を参照して下さい。
【年収別】フリーランスエンジニアの手取り・税金額
では実際にフリーランスエンジニアとして働いた場合、どの程度の税金が引かれ手取り収入が大体いくらくらいになるのか、ざっくり年収別に見ていきましょう。
年収300万円
まずは、年収が約300万円の場合です。
経費を30%程度と仮定して計算してみましょう。
支払わなければならないものとしては、
| 国民健康保険料 | 約10万円 |
| 国民年金 | 約20万円 |
| 住民税 | 約10万円 |
| 所得税 | 約5万円 |
となり、年収からこれらを引くと手取り収入としては約255万円となります。
経費分は控除として計算されますが、ここから業務に必要なものを購入しなければならないこともあるため、実際に手元に残る額としてはもう少し減ってしまいます。
月収としても諸経費を引くと20万円を切る額となり、生活していくためには多い金額だとは言えませんね。
年収500万円
次に年収が500万円程度になった場合です。
こちらも経費は約30%として計算していきましょう。
保険や納税額の目安としては、
| 国民健康保険料 | 約25万円 |
| 国民年金 | 約20万円 |
| 住民税 | 約25万円 |
| 所得税 | 約15万円 |
程となります。
年収の500万円からこれらを引くと、約415万円が手取り収入となりますね。
月収としては単純計算で35万円以下くらいになりますが、やはり諸経費などを考えるともう少し低い額と考えておいた方が良いでしょう。
年収1,000万円
続いて、年収が1000万円程度となった場合です。
経費を30%程度と仮定すると支払わなければならない額の目安としては、
| 国民健康保険料 | 約60万円 |
| 国民年金 | 約20万円 |
| 住民税 | 約60万円 |
| 所得税 | 約75万円 |
程度となります。
これらを引いた単純な手取り収入としては、約785万円になります。
すでに年間200万円以上もの額が引かれていますが、さらに年収1000万円を超えると2年後には消費税を支払わなければならなかったり、8万円程度の個人事業税がかかってきたりします。
計算上、フリーランスの収入としてはざっくり7割程度が手取りになると考えておくのが良さそうですね。
フリーランスエンジニアの節税方法4選
フリーランスエンジニアが納めなければならない税金の種類や大体の金額をご紹介しましたが、こうして実際に考えるとできるだけ抑えて手取りを増やしたいところですよね。
そのためには、節税対策を行うことが大切です。
フリーランスエンジニアにおすすめな節税対策を4つ、ご紹介したいと思います。
青色申告を行う
まずは確定申告の際に、青色申告を行うことです。
青色申告には事前に承認申請が必要だったり、複式簿記による帳簿付けや損益計算書などを添えなければいけないといった複雑な点は多いのですが、これを行うことで簡易的な白色申告では受けられない特別控除が受けられます。
最大で約65万円控除されますので、きちんと青色申告での申告をすることをおすすめします。
漏れなく経費計上する
経費分の所得は課税対象にならないため、業務に関する出費はなるべく漏れがないように経費として計上することも大切です。
自宅を職場にしているフリーランスエンジニアは家賃や光熱費、通信費などの一部も経費として計上できますので、経費にできる分はなるべく計上して税額を抑えましょう。
iDeCoや小規模企業共済に加入する
私的年金制度のひとつであるiDeCo(個人型確定拠出年金)や、個人事業主や小規模企業役員などが廃業の際の備えとするための共済制度、小規模企業共済などに加入するのもおすすめです。
どちらも掛金が全額控除対象になり節税効果があるほか、共済金や給付金の受け取りの際にも税制優遇を受けられます。
掛金も範囲内で自分で決められますので、無理のない範囲で加入してみてはいかがでしょうか。
事業が発展したら法人化する
事業が発展し収入が十分に増えたら法人化することをおすすめします。
法人化すると個人の所得にかかる所得税ではなく法人税の課税になります。
具体的には控除後の課税対象となる所得が330万円を超えると法人税の税率の方が低くなり、節税になりますね。
法人化するための費用や他の課税額なども考慮してメリットが上回る時には法人化を考えてみても良いでしょう。
まとめ
今回の記事では、フリーランスエンジニアとして働き始めたばかりで確定申告や税金問題などに不安があるという方に向けて、実際にどんな税金がどの程度かかるのか、節税対策も合わせてご紹介しました。
自由に業務を行い高収入を得られるイメージのあるフリーランスですが、支払わなければならない税金や自ら行わなければいけない手続きが多くあります。
節税対策をしっかりと行い、フリーランスエンジニアとしての手取りを増やしていけると良いですね。